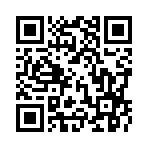2019年10月07日
琵琶湖のスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の分布
 琵琶湖の南湖の東岸、木の浜で見かけたスクミリンゴガイの卵塊。
琵琶湖の南湖の東岸、木の浜で見かけたスクミリンゴガイの卵塊。湖畔のヤナギに鈴なりになっている。
石積み護岸や水路のコンクリートにも産卵はする。
だけど直射日光が当たればタンパク質が変質する温度に上がりそうだ。
だから貝も産卵に適した植物を選んでるんだろう。
スクミリンゴガイの日本での歴史は比較的新しく1980年代。
滋賀県でも1986年に現野洲市付近で見られ2012年には生息調査が行われている。
参考文献: 2012 年度 第1 回調査
スクミリンゴガイおよびタニシ類の分布調査結果報告
 参考文献の2012年スクミリンゴガイの分布図。
参考文献の2012年スクミリンゴガイの分布図。野洲川は北湖だが現在は南湖にかなり広がっていると思われる。
ところで良く行く伊庭内湖では卵塊を見ない。
付近の北湖の愛知川河口や大同川河口辺りでも見ない。
やがては貝の歩くスピードで北にも分布が広がって来るんだろうか。
にほんブログ村 ↑ 秋だからポチっとな
貝の歩くスピード?
カタツムリで0.05km/hって記載もある。
冬季は活動が鈍るだろうし、盛期でも色んな妨げを考慮して仮に0.01km/hってかなり減速して考えてみても・・・
1986年から2019年までの13年間に1000kmくらいは進めてしまう。
野洲川河口から大同川河口まで直線で15km程度、湖岸線の複雑さを考慮して歩く距離を5倍にしても75kmか・・・
既に分布を広げててもおかしくない距離のような気がする。
貝にとって障壁となる<何か>があると考えた方が良いんじゃないか?
障壁は(ヒトから見れば気付かないような)単純なもののように思える。
カタツムリで0.05km/hって記載もある。
冬季は活動が鈍るだろうし、盛期でも色んな妨げを考慮して仮に0.01km/hってかなり減速して考えてみても・・・
1986年から2019年までの13年間に1000kmくらいは進めてしまう。
野洲川河口から大同川河口まで直線で15km程度、湖岸線の複雑さを考慮して歩く距離を5倍にしても75kmか・・・
既に分布を広げててもおかしくない距離のような気がする。
貝にとって障壁となる<何か>があると考えた方が良いんじゃないか?
障壁は(ヒトから見れば気付かないような)単純なもののように思える。
Posted by like a stream at 01:11│Comments(2)
│スクミリンゴガイ
この記事へのコメント
僕の勝手な感想ですが、近年琵琶湖の生態系が変化したような気がしてます。ブラックバス&ブルーギル激減、小鮎も激減、ウィード激減、水質が異常にクリア。
温暖化の影響で、冬に起こるべき全湖レベルのターンオーバーが起きてないという噂も聞きます。
温暖化の影響で、冬に起こるべき全湖レベルのターンオーバーが起きてないという噂も聞きます。
Posted by popper at 2019年10月27日 14:29
popperさん、ようこそ。
>僕の勝手な感想ですが、近年琵琶湖の生態系が変化したような気がしてます。
同様に感じます。
20年前は北湖でももっとウィード帯がモリモリ有りました。
シラハエもフナもバスも見える魚が減ってしまいましたね。
何なんでしょうね。
>僕の勝手な感想ですが、近年琵琶湖の生態系が変化したような気がしてます。
同様に感じます。
20年前は北湖でももっとウィード帯がモリモリ有りました。
シラハエもフナもバスも見える魚が減ってしまいましたね。
何なんでしょうね。
Posted by release-windknot at 2019年10月28日 21:02
at 2019年10月28日 21:02
 at 2019年10月28日 21:02
at 2019年10月28日 21:02