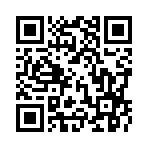2011年12月08日
琵琶湖でのバスの駆除は効果があったのか

リリース禁止に駆除の効果など無いので税金を使っては無駄だ。
そもそも釣りは資源を枯渇させない優良な漁法。
回復するに十分な個体数を残して簡単には釣れなくなってしまうが故に資源が守られる。
関連記事釣りと魚の資源量の関係
しかし多少でも駆除の上乗せになるのでは?との考えもあるので駆除そのものの評価をしてみた。
私はリリース禁止条例に反対しているのであって、漁獲に反対しているわけではない。
漁師がギル・バスを獲るのは当然。
効率的に獲れるのであれば食材のほかペットフードなり肥料なり有効活用の道がある。
琵琶湖では外来魚に食べられてニゴロブナやホンモロコなど有用魚種の漁獲が減少したと言われ、そのことが問題視されてきた。
有用魚種の漁獲の回復のために葦帯の復活やいろんな試みが行われている。
外来魚の駆除は有用魚種の漁獲の回復という目的のための手段でもある。
外来魚の駆除が本格化して、直接経費だけで毎年1億円~3億円近い税金を使って駆除が続いた。
平成初期のころ、推定生息量3000(バスは500)トンだった外来魚が21年末時点で半減以下の1400(バス300)トン。
駆除の効果のように見えるが、どの年の駆除量も控えめな自然回復係数0.4を下回る。
1年で回復するに十分な生息量を残した駆除しかしていないのに減少に至っている。
参考資料水産統計琵琶湖漁業魚種別漁獲量
バスが500トン以上生息していたらしい1990年ころは、漁獲合計で4800トン程の水揚げがあった。
駆除によって外来魚を選択的に取り除いた。
駆除の効果が有ったならば空いたスペースを埋めるのは在来魚のはず。
だがどの魚種もどんどん減っている。
平成21年度には漁獲合計が1560トンに。
聞こえてくる話によると今年はもっと少なくなっているように思える。
漁獲が減ったのは漁業者が高齢化などにより減ったから、と言う話もある。
しかしニゴロブナとホンモロコは高値の魚であり、放流もされ増やそうとしている魚。
特にこの2種は増えれば漁獲に現れるはずなのだ。
バスの駆除が統計に載り始めて25年。
時々「駆除の効果で在来魚の復活の兆しが見える」と言う大本営の発表はあった。
だが滋賀県の駆除の部署も効果をチェックするべき機関も、駆除の効果と漁獲の減少の関係について触れない。
正義の思想が支配する組織の中では気付いても言い辛いのかも。
毎年駆除ができて成果に拍手してまた予算を組む。
外部の同じ思想の人からも評価され、精神的に正義感も満たされる。
問題視されなければそれが続いても良いような気もする。
けど本来の目的に対する効果がなければ税金の使用方法としてはもったいないはず。
もう駆除で直接経費だけで何十億円か使ったはず。
バスもすべての魚も減り続けている(富栄養化が好きなワカサギは別だった)。
バスが魚の減少の要因ではあるだろうけれども主要因ではなかった。
そのことを踏まえてもっと在来種や有用魚種や漁獲の復活を考えても良いのでは。
もっと有効に税金の効果を出す手段はあるはず。

にほんブログ村↑正義の強要よりも実が生ることが大事だと思う
考えうる魚の減少の主要因は
1.琵琶湖総合開発やダムによる流入河川の分断や内湖の埋め立てなどを含む、湖岸線の単調化。
2.92年から運用された、梅雨の産卵期に減水させる水位操作。
3.干拓地などの排水路からの良くない水の流入などの、水質の変化。
次回、これへの対処を書くつもり。
漁師がギル・バスを獲るのは当然。
効率的に獲れるのであれば食材のほかペットフードなり肥料なり有効活用の道がある。
琵琶湖では外来魚に食べられてニゴロブナやホンモロコなど有用魚種の漁獲が減少したと言われ、そのことが問題視されてきた。
有用魚種の漁獲の回復のために葦帯の復活やいろんな試みが行われている。
外来魚の駆除は有用魚種の漁獲の回復という目的のための手段でもある。
外来魚の駆除が本格化して、直接経費だけで毎年1億円~3億円近い税金を使って駆除が続いた。
平成初期のころ、推定生息量3000(バスは500)トンだった外来魚が21年末時点で半減以下の1400(バス300)トン。
駆除の効果のように見えるが、どの年の駆除量も控えめな自然回復係数0.4を下回る。
1年で回復するに十分な生息量を残した駆除しかしていないのに減少に至っている。
参考資料水産統計琵琶湖漁業魚種別漁獲量
バスが500トン以上生息していたらしい1990年ころは、漁獲合計で4800トン程の水揚げがあった。
駆除によって外来魚を選択的に取り除いた。
駆除の効果が有ったならば空いたスペースを埋めるのは在来魚のはず。
だがどの魚種もどんどん減っている。
平成21年度には漁獲合計が1560トンに。
聞こえてくる話によると今年はもっと少なくなっているように思える。
漁獲が減ったのは漁業者が高齢化などにより減ったから、と言う話もある。
しかしニゴロブナとホンモロコは高値の魚であり、放流もされ増やそうとしている魚。
特にこの2種は増えれば漁獲に現れるはずなのだ。
バスの駆除が統計に載り始めて25年。
時々「駆除の効果で在来魚の復活の兆しが見える」と言う大本営の発表はあった。
だが滋賀県の駆除の部署も効果をチェックするべき機関も、駆除の効果と漁獲の減少の関係について触れない。
正義の思想が支配する組織の中では気付いても言い辛いのかも。
毎年駆除ができて成果に拍手してまた予算を組む。
外部の同じ思想の人からも評価され、精神的に正義感も満たされる。
問題視されなければそれが続いても良いような気もする。
けど本来の目的に対する効果がなければ税金の使用方法としてはもったいないはず。
もう駆除で直接経費だけで何十億円か使ったはず。
バスもすべての魚も減り続けている(富栄養化が好きなワカサギは別だった)。
バスが魚の減少の要因ではあるだろうけれども主要因ではなかった。
そのことを踏まえてもっと在来種や有用魚種や漁獲の復活を考えても良いのでは。
もっと有効に税金の効果を出す手段はあるはず。
にほんブログ村↑正義の強要よりも実が生ることが大事だと思う
考えうる魚の減少の主要因は
1.琵琶湖総合開発やダムによる流入河川の分断や内湖の埋め立てなどを含む、湖岸線の単調化。
2.92年から運用された、梅雨の産卵期に減水させる水位操作。
3.干拓地などの排水路からの良くない水の流入などの、水質の変化。
次回、これへの対処を書くつもり。
Posted by like a stream at 00:42│Comments(7)
│滋賀県の獲ったら殺せという正義の思想を強要する条例に反対します
この記事へのコメント
私の記憶では、北海道の某湖でのこと、
年々漁獲量が減っているそうです、特に水質汚染や水位の変化は無いのにです、
原因は人間が魚を獲る事により、湖の中の生物に必須の要素が減少したからだそうです、
たしかそれはリンだったと記憶しています、(違ったらごめんなさい)
この必須物質の絶対量により、湖の生物の絶対量も決まる、そしてこの物質を人間がどんどん湖から持ち去るので、
その湖の生物の絶対量が減少していくのだそうです、
人が奪わなければ湖の中で物質は循環しますし、海からの遡上魚がいれば補充されます、
しかし現在は、湖からの流出河川にはダムがあったり、河口には遡上魚を獲る網があったりして補充はされません、
北海道の湖と琵琶湖ではかなり条件が違うとは思いますが、こんな理由はないでしょうか?
年々漁獲量が減っているそうです、特に水質汚染や水位の変化は無いのにです、
原因は人間が魚を獲る事により、湖の中の生物に必須の要素が減少したからだそうです、
たしかそれはリンだったと記憶しています、(違ったらごめんなさい)
この必須物質の絶対量により、湖の生物の絶対量も決まる、そしてこの物質を人間がどんどん湖から持ち去るので、
その湖の生物の絶対量が減少していくのだそうです、
人が奪わなければ湖の中で物質は循環しますし、海からの遡上魚がいれば補充されます、
しかし現在は、湖からの流出河川にはダムがあったり、河口には遡上魚を獲る網があったりして補充はされません、
北海道の湖と琵琶湖ではかなり条件が違うとは思いますが、こんな理由はないでしょうか?
Posted by CREEK WALKERS at 2011年12月09日 20:25
そりゃあ“バスに口無し”。
魚に責任をなすりつけてりゃ、八方丸く収まるってもんです。
素人考えでも有用魚種を含めた魚(その他水棲生物)の減少は、富栄養化をはじめとする環境変化(悪化)が主要因ではないかと思います。
そっちに手をつけようとすると色々差しさわりがあるでしょうし、結局は人は易きに流れるということですかね。
またまたダークなblueでした。
魚に責任をなすりつけてりゃ、八方丸く収まるってもんです。
素人考えでも有用魚種を含めた魚(その他水棲生物)の減少は、富栄養化をはじめとする環境変化(悪化)が主要因ではないかと思います。
そっちに手をつけようとすると色々差しさわりがあるでしょうし、結局は人は易きに流れるということですかね。
またまたダークなblueでした。
Posted by blue at 2011年12月09日 23:39
琵琶湖総合開発以来、湖岸線が単調になって、魚が減ったのは事実ですね。
魚が取れなくなって、漁師も減りました。
それ以前は今の琵琶湖博物館のあたりなんて、でかい湿地帯で、水鳥と魚の楽園のようでした。埋め立ててできた博物館の中から自然保護とか言ってる人たちは一体・・・と思います。
駆除対策費用は全部養殖&放流に使えば少しは足しになったかもしれません。駆除の間引き効果でバスは大型化しましたがw
魚が取れなくなって、漁師も減りました。
それ以前は今の琵琶湖博物館のあたりなんて、でかい湿地帯で、水鳥と魚の楽園のようでした。埋め立ててできた博物館の中から自然保護とか言ってる人たちは一体・・・と思います。
駆除対策費用は全部養殖&放流に使えば少しは足しになったかもしれません。駆除の間引き効果でバスは大型化しましたがw
Posted by けざわひがし at 2011年12月11日 14:00
CREEK WALKERSさん、ようこそ。
人間が持ち去ることにより栄養分の絶対量が不足していく話、とても勉強になりました。
昭和30年代に琵琶湖の下流に天ケ瀬ダムができるまでは、大阪湾からウナギやサツキマスやアユなどが遡上したそうです。
漁獲統計を見るとその頃からの落ち込みも大きいので、海から補充されるべき栄養分の遮断も有るのかもしれません。
blue さん、ようこそ。
とりあえず悪者を作っておけば正義の立場に立てて一安心・・・かも。
けざわひがしさん、ようこそ。
昔を知る地元の住民からすれば、魚が減って当然っていう大きな変化でしょうね。
駆除費用を湖岸線の複雑化に回せれば、少しは漁獲の底上げが期待できると思います。
人間が持ち去ることにより栄養分の絶対量が不足していく話、とても勉強になりました。
昭和30年代に琵琶湖の下流に天ケ瀬ダムができるまでは、大阪湾からウナギやサツキマスやアユなどが遡上したそうです。
漁獲統計を見るとその頃からの落ち込みも大きいので、海から補充されるべき栄養分の遮断も有るのかもしれません。
blue さん、ようこそ。
とりあえず悪者を作っておけば正義の立場に立てて一安心・・・かも。
けざわひがしさん、ようこそ。
昔を知る地元の住民からすれば、魚が減って当然っていう大きな変化でしょうね。
駆除費用を湖岸線の複雑化に回せれば、少しは漁獲の底上げが期待できると思います。
Posted by release-windknot at 2011年12月12日 00:36
at 2011年12月12日 00:36
 at 2011年12月12日 00:36
at 2011年12月12日 00:36バサー氏ねw
Posted by あ at 2012年12月12日 00:17
バスのせいじゃない護岸化とかがげいいん
バサー氏ねってゆってるけどモラルを意識しているバサーもいる。
ごみひろいもする。
簡単に氏ねと言われても困る!!!!!!!!
バサー氏ねってゆってるけどモラルを意識しているバサーもいる。
ごみひろいもする。
簡単に氏ねと言われても困る!!!!!!!!
Posted by 秘密 at 2014年08月08日 18:20
秘密さん、ようこそ。
以前の記事まで読んでいただいてありがとうございます。
以前の記事まで読んでいただいてありがとうございます。
Posted by release-windknot at 2014年08月11日 23:56
at 2014年08月11日 23:56
 at 2014年08月11日 23:56
at 2014年08月11日 23:56※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。